CSWSてんかんとは
どのような病気でしょうか?
睡眠時の脳波検査で特徴的な脳波異常をもつ、幼小児期にみられるてんかんです。
この脳波異常とともに知的・認知機能の退行や行動面の問題などがみられます。てんかん発作が初めてみられる年齢は2ヵ月〜12歳頃までさまざまですが、4〜5歳頃に最も多く出現します。
この病気の原因はまだ確定できていません。しかし、一部の患者さんでは遺伝子の異常が最近みつかっています。このてんかんをもっている人の30〜60%で画像検査に異常がみられます。また、周産期血管障害、皮質形成異常、多小脳回、水頭症などを伴っている ことがあります。
多くの患者さんで、睡眠中に持続する特徴的な脳波異常は思春期頃までになくなります。しかし、一部の患者さんでは、脳波所見が改善した後も発作が残る場合があります。また、発作がなくなり脳波が改善しても、行動障害や知的レベルの低下、言語聴覚障害、運動障害などが残ることがあります。なお、国際抗てんかん連盟により、睡眠時棘徐波活性化を示すてんかん性脳症と名称変更されています。
どのような症状がありますか?
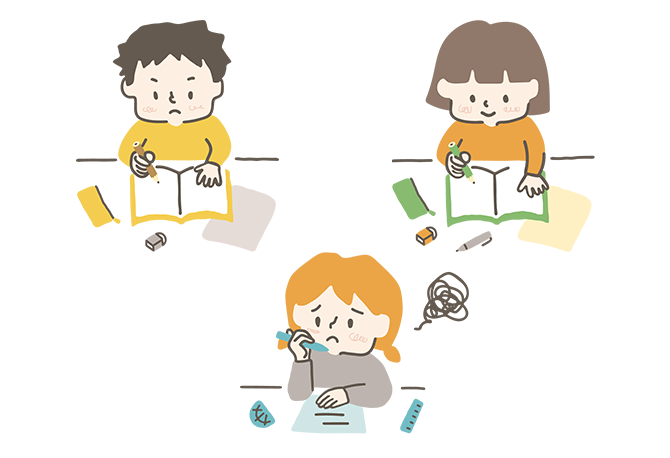
けいれんや意識が障害される発作など、いろいろなタイプのてんかん発作がみられます。
また、学習面での低下や言葉の障害、発達障害を含む行動変化、運動障害など、程度はさまざまですが生じてきます。
どのような検査が必要ですか?
覚醒時に加え睡眠時の脳波検査や背景疾患をみつけるための画像検査が必要です。
どのような治療がおこなわれますか?

抗てんかん薬を使用します。抗てんかん薬以外にもステロイド療法や食事療法が有効であったという報告があります。
各種治療に関わらず神経心理学的な遅れが進むあるいは停滞し、てんかん発作の原因となる大脳の病変がみられる場合には外科的治療が有効なこともあります。
運動・高次脳機能の障害に対しては、リハビリテーションが役に立つ場合があります。
生活上で注意することはありますか?
発作症状だけではなく、発達や運動・高次脳機能についても注意して経過をみていくことが必要です。知的面・行動面の問題に関しては、学校関係者や周囲の方にも病気を理解してもらい、障害特性に応じた対応が必要になることがあります。
参考文献:てんかんの難病ガイド「希少てんかんに関する包括的研究」班
CSWS治療について(家族会員に聞き取り調査しました)
CSWSの原因とされるもの
- 原因不明(MRI異常なし)
- 視床出血
- 出生時の感染症
- 幼少期の急性脳炎
- 周産期血管障害(新生児仮死)
※一部のCSWS患者ではSRPX2、ELP4、GRIN2A遺伝子の変異が見つかっていると言われていますが、現会員で遺伝子変異が見つかっている方はいません(検査結果待ちあり)
てんかん発作と脳波改善に対して/抗てんかん薬(順不同)
- ベンゾジアゼピン(BZD) 系
ジアゼパム(DZP): セルシン、ホリゾン、ダイアップ(ジアゼパム座薬)、ジアゼパム大量療法
クロパゼム(CLB):マイスタン
クロナゼパム(CZP):リボトリール、ランドセン
ニトラゼパム(NZP):ベンザリン
ミダゾラム(MDL):ブコラム、ミダフレッサ(注射剤) - バルプロ酸(VPA):セレニカ、デパケン
- エトスクシミド(ESM):エピレオプチマル、ザロンチン
- スルチアム(STM):オスポロット
- レベチラセタム(LEV):イーケプラ
- ラモトリギン(LTG):ラミクタール
- ラコサミド(LCM):ビムパット
- ニサミド(ZNS):エクセグラン
- クロラゼプ酸(CLZ):メンドン
- フェニトイン(PHT):アレビアチン
- アマンタジン(パーキンソン病治療薬)
その他の治療(順不同)
- ステロイド治療:ステロイドパルス療法、経口ステロイド(プレドニゾロン)
- ACTH療法
- ガンマグロブリン療法/免疫グロブリン療法
- 外科的治療:脳梁離断
- 睡眠障害:メラトベル
- 行動障害(多動):インチュニブ、エブリファイ、コンサータ、リスペリドン


